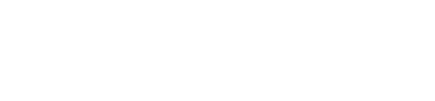2025年、平和軍縮時評
2025年04月30日
ガザ・ジェノサイドにおけるデュアルユース問題と日本の責任
役重善洋
1.はじめに~ガザにおけるジェノサイド作戦の長期化と欧州における対イスラエル制裁に向けた動き
ガザ地区では3月2日よりイスラエルによる人道支援物資の搬入妨害が続いており、乳幼児や高齢者を中心に大量の餓死者が出続けている。そうした状況の中でイスラエルは「ハマースの殲滅」が最優先課題だとして人口密集地への爆撃を続け、グテレス国連総長をしてガザが「殺戮の場」となっていると言わしめた(4月8日)。
この状況に対し、欧州ではイスラエルに対する武器禁輸等の制裁に向け、これまで重かった足取りがようやく加速し始めている。オランダはイスラエル向けの軍事装備品やデュアルユース(軍民両用)製品の輸出規制を強化する決定を4月7日に行った。また、スペインは、4月にイスラエルからの銃弾購入契約を破棄し、武器禁輸への動きを強めている。EUとイスラエルの貿易協定見直しを求める声も高まっている。
2.ジェノサイド下で伸びるイスラエルの武器輸出
ここで、注意しなければならないのは、そもそもEUは27か国をまとめて見れば、輸出入額とも米国や中国を上回るイスラエル最大の貿易相手であり、しかもガザでのジェノサイドが続いた2024年に前年より貿易額が伸びているということである。イスラエルの武器輸出は過去4年間伸び続けており、2024年には欧州が武器輸出額全体の54%(前年度は35%)を占めている。ついでに言えば、2020年のアブラハム合意でイスラエルと国交を結んだアラブ諸国(UAE・バハレーン・モロッコ・スーダン)のイスラエルからの武器購入額が12%(前年度は3%)も占めている。つまり、ガザにおけるジェノサイドは、少なくとも開始から1年余りの間、イスラエルの武器ビジネスにとってネガティブな影響を与えているとは言えず、むしろプラスの方向に働いた可能性さえあるのである。
これらの武器のおよそ半分は、防空システムやミサイル、ロケットなどであり、その背景には、欧州諸国がウクライナ戦争でロシアのミサイル攻撃能力を目の当たりにし、ミサイル防衛能力強化の必要性を認識したこと、ウクライナ支援で減らした武器・弾薬のストックの補充が求められたことがある。このことについて、イスラエルのカッツ国防相は次のように述べている。
「この巨大な成果は、ガザのハマース、レバノンのヒズブッラー、イエメンのフーシ―派、イランのアヤートッラー体制、他、我々がイスラエルの敵と戦っている地域におけるイスラエル軍および防衛産業の成功に直接起因するものである。」
この発言は、プロパガンダとしての性格を割り引いて考える必要があるにせよ、イスラエルの軍需産業の競争優位性が、パレスチナ被占領地における実地試験の機会をふんだんに有していることに大きく依拠している現実をも示している。ミサイル防衛システムの開発において米国がイスラエルの軍需産業と長年、一体的ともいえる協力関係を保ってきたことの理由の一端もそこにある。
なお、イスラエルの軍需産業の花形であった無人機の輸出は、中国にシェアを奪われ2024年度武器輸出額の1%以下に大きく落ち込み、高性能ドローンに特化する販売戦略に移行している。防衛省によるイスラエル製攻撃型ドローン導入が現在も検討されている。深まる米中対立の米国側に位置する日本はイスラエルにとって重要なマーケットとなっている。
3.イスラエル経済におけるデュアルユース・ビジネスの重要性
このように、イスラエルがパレスチナ被占領地を中心に、日常的に軍事的・諜報的活動に従事していることが、経済的にプラスの意味を持つようになったのは比較的最近のことである。1993年のオスロ合意(イスラエルとパレスチナ解放機構の間で結ばれた和平合意)は、イスラエルが経済自由化を進める上で障害となっていた「占領の負荷」を取り除こうとしたことが重要な背景となっていた。1990年代、「和平ムード」の下で多国籍企業のイスラエル進出やイスラエル企業の海外進出が続くが、90年代も終わりに近づくと被占領地における入植地建設など、イスラエルがパレスチナ独立を容認する意志を持たないことが次第に明確となり、2000年の第二次インティファーダ(反占領民衆蜂起)勃発を迎えることとなった。好調だったイスラエル経済は大きな痛手を受けることになるが、同時に、イスラエル軍のIT部隊出身者による起業を国家ぐるみで支援し、「対テロ戦争」でセキュリティ意識が高まった米国市場を主なターゲットとして、軍から生まれた技術であることを積極的に打ち出し、人的・資本的な提携を深めた。
この経緯においてデュアルユース問題が大きな意味をもつことに注意が必要である。2000年代以降イスラエルは武器輸出に力を入れるようになり、国民一人当たりの武器輸出額で世界一位となるが、いずれにせよ武器輸出による収入は極めて不安定なものである。そこで軍民両用のデュアルユースを開発するスタートアップへの海外投資やデュアルユース製品・サービスの開発・輸出が極めて重要になる。イスラエルのITセクターは過去25年、軍需産業の民営化・グローバル化と相俟って急速な成長を見ており、2024年でGDPの20%、総輸出額の53%を占める最大の産業となっている。このIT産業を支えるスタートアップ企業の多くはイスラエル軍関係者が立ち上げたものであり、サイバーセキュリティ関連が中心である。そして、これらの企業に対する直接投資やM&A(合併・買収)がイスラエル経済の慢性病ともいえる貿易赤字を埋め合わせるかたちになっている。したがって、イスラエル経済は、米国による年間40億ドルの軍事援助に加え、絶え間ない対内直接投資がなければ立ち行かない構造になっている。
雇用創出力が弱いIT産業への過度の傾斜は、貧困率・経済格差の大きさに反映されている。2023年のイスラエルの貧困率は、 10月7日のガザ抵抗勢力決起後の避難者等への政府の緊急支援策をもってしても20%、OECD諸国(経済協力開発機構)の中でコスタリカに次ぐ2番目の高さとなっている。ただし、イスラエル内のパレスチナ市民の貧困率は倍近くあり、さらにガザを含む被占領地のパレスチナ人の貧困率は74.3%となっている。残念ながらイスラエルにおける経済的矛盾は、政府の政策に対する批判よりも、パレスチナ人に対するレイシズム(人種差別)というかたちで表出している。「敵」への憎悪・恐怖を持続させることが内部矛盾を覆い隠すためにますます必要となっている。
4.安倍政権の「科学技術イノベーション総合戦略」と日本・イスラエル関係の緊密化
このようなイスラエルの経済的要請を背景として2010年代より、イスラエルを「スタートアップ・ネーション」とブランディングし、その軍産学複合モデルを「エコシステム」として宣伝する動きが日本においても始まった。この動きは、2011年の東日本大震災に際してのイスラエル軍医療部隊派遣を一つの突破口とし、翌年成立した第二次安倍政権が進める「科学技術イノベーション総合戦略」の方向性と合致するかたちで全面的に受け入れられることになった。
安倍政権は、日本経済の長期不況からの脱却と軍事力強化という二大目標を同時に追求するため、イスラエルの軍産学複合モデルに学ぼうとしたように思われる。2013年に策定した「科学技術イノベーション総合戦略」では、「国家存立の基盤である国家安全保障・基幹技術等の研究開発を強力に推進し、全体としてイノベーションの芽を創造できる体制となるよう、大学や研究機関は自ら進んで組織の運営方法や資源の活用方法を再構築し活性化する必要がある」とした。2014年5月のネタニヤフ首相来日に際しては、両国間の「包括的パートナーシップの構築に関する共同声明」が発出され、「サイバーセキュリティに関する協力の必要性」や「防衛協力の重要性」などが確認された。この年の夏にはガザに対する51日間にわたる大規模攻撃が行われたが、その最中にベンチャーキャピタル「サムライ・インキュベート」はテルアビブ事務所を設立し、レピュテーションリスクを危惧する日本企業とイスラエルのスタートアップ企業との提携推進の広告塔となった。
2015年1月には、イスラエルの国家サイバー局(2012年設立)に類似した内閣サイバーセキュリティセンターが設置された。また、この年、安全保障技術研究推進制度(防衛省ファンド)が発足し、「防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し、先進的な基礎研究を公募する」こととなり、大学における軍事研究に強力な予算上のインセンティブが与えられることになった。これに対し、日本学術会議は「軍事的安全保障研究に関する声明」(2017年3月)で「政府による研究への介入が著しく、問題が多い」と真っ向から批判した。このことは、2020年の菅政権による学術会議会員6名の任命拒否の動きへとつながった。
なお、オバマ政権末期から第一次トランプ政権にかけての時期は、「ビジネスと人権」への関心の高まりとも相俟って、イスラエルに対するBDS(ボイコット、資本引揚げ、制裁)運動が飛躍的な拡がりを見せた時期であった。さらに国連人権理事会においてイスラエルの入植地ビジネスにかかわる企業のデータベースを作成することが決議されたり、あらためて安保理で入植地建設を違法とする決議が採択されたりするなど、イスラエルの「エコシステム」をグローバル化しようとする戦略に対して国際的な圧力が強まった。
しかし、安倍長期政権の下、2017年5月には日本イスラエル投資協定が締結され、2018年8月には、日本では初となるイスラエルの軍事見本市ISDEFが川崎市で開催、同年11月には、イスラエルとのサイバーセキュリティ分野における協力に関する覚書が署名されるなど、強引に「エコシステム」導入の地ならしともいえる動きが続いた。また、この年、ジェトロのテルアビブ事務所は「アラブボイコット調査成果報告書」を発表した。この報告書の第二部は、イスラエルのテルアビブ大学付属国家安全保障研究所(INSS)にBDS運動に関する調査報告を依頼し、その内容をそのまま掲載したもので、「日本企業がイスラエル企業と経済関係を強めることでBDS運動の対象になる可能性は低い」と結論づけていた。
5.菅政権下で政策と融合する「スタートアップ・エコシステム」
菅政権下で策定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(2021年)では、初めて「エコシステム」の語が登場し、「総合的な安全保障」といった言葉遣いとともに、「軍」と「民」を分け隔てないことが、「持続可能で強靭な社会」創出に向けたイノベーションに不可欠とのメッセージが強調された。イスラエルがこの動きを重要なビジネスチャンスと考えたことは当然といえる。菅政権下で進んだ日本企業のイスラエル進出に関して注目が必要なものとしては、富士通がベングリオン大学内にサイバーセキュリティセンターを設立したこと、ソフトバンクがイスラエル事務所開設にあたりヨシ・コーヘン元モサド長官を所長に任命したこと、NTTがイスラエルに技術探索拠点を設立するにあたりノア・アッシャー前駐日イスラエル経済公使を代表に任命したこと、などがある。いずれも2021年中の出来事である。
ところで、イスラエルと日本の関係強化の契機となったのが東日本大震災におけるイスラエル軍医療部隊の派遣であったことは先に述べたが、その後もイスラエルは東北地方で国策援助団体「イスラエイド」の日本法人を立ち上げたり、イスラエル企業ネタフィムの点滴灌漑システムを導入した水田を関連NPOを通じて運営したりしていた。東北に日本進出のチャンスを見出そうとするイスラエルの動きは、東北出身の菅義偉が首相になって以降、新たな展開を見せつつある。2019年に「スタートアップ・エコシステム拠点都市選定」に選ばれた仙台市で2021年より2年がかりの「東北-イスラエル・スタートアップ・グローバルチャレンジ・プログラム」が実施されたり、「福島ロボットテストフィールド」(2019年設置)を軸に町おこしをしようとする南相馬市で「イスラエル企業オンラインピッチ」が開催されたりした(2022年)。2021年にはイスラエル大使一行が東北大学を訪ね、総長・理事らと「スタートアップ・技術移転・イノベーション領域における東北地方とイスラエルとの協力の可能性」などについて意見交換をした。さらに2024年6月、東北大学は最初の「国際卓越研究大学」として認定基準を満たしたとの発表があると、9月にはヘブライ大学学長らが東北大学を訪問するなど、機敏な動きを見せている。
6.おわりに
これまでに述べたことをまとめておく。ガザで起きているジェノサイドは、少なくともイスラエル経済の軍事セクターおよびそれと深く結びついたITセクターにとってプラスに作用している側面がある。その主要な理由として、少なくとも二点を指摘することができ、いずれも、イスラエルが抱える安全保障上の課題と類似した課題に直面していると認識する国が増えていることと関係している。
第一に、主要な戦争の形態においてミサイルや無人機の位置づけが大きくなっており、そうした戦争に必要とされる「実地試験済み」の兵器への需要が高まっていること、第二には、民主主義制度の弱体化やSNSを通じた情報戦の拡大などを背景として、各国政府や大手企業においてサイバーセキュリティ技術への需要が高まっていることを挙げることができる。少なくともこの要因だけを考えれば、イスラエルがこの間の戦闘で誇示してきたミサイル防衛システム「アイアンドーム」によるロケット弾迎撃や、高度な諜報能力にもとづく暗殺作戦などは、イスラエルの軍事・セキュリティ産業の「広告」としての意味合いを持つ。この構造がイスラエルのジェノサイド作戦の長期展開を可能とする要因となっている。
もちろん、イスラエルのジェノサイド作戦を終わらすことができない最大の要因は米国のイスラエルに対する軍事的・政治的支援である。しかし、軍国化・警察国家化を強める日本がイスラエルの軍事・セキュリティ産業に接近し、とりわけサイバーセキュリティなどのデュアルユース領域において官民挙げての協力関係を築いてきたことも、イスラエルの「エコシステム」を肥大化させることでガザのジェノサイドを誘引し、その長期化を可能とする重要な要因となっていることは否定し得ない。
デュアルユース技術をめぐるイスラエルとの協働は、経済的にイスラエルのジェノサイドを支えるだけでなく、より直接的な意味を持つ。イスラエルがガザ攻撃でターゲットとすべき建物や人物を短時間でリスティングするのに、AIプログラムを利用していることが関係者の証言によって明らかにされている。このイスラエル軍のAI利用についてはグーグルがクラウドサービス等を提供していることがやはり内部リークで暴露され、2024年4月には、米国でこれに抗議した従業員50名が解雇された。日本の企業も例外ではない。例えばファナック社製ロボットがイスラエルの軍需企業エルビット・システムズ社の砲弾製造工場で使用されていることがイスラエル国防省の宣伝映像から明らかになり、イスラエルへのデュアルユース製品輸出規制を要請する動きへと展開している。
誰もが今のような状況が望ましいことではないと気付きながらも、「国益」という狭い世界観の中、破局を予感しながらも軍事的緊張をエスカレートさせていくコースを修正する有効な道筋を見出せずにいるように感じる。日本は近代化の過程において、侵略戦争拡大の泥沼に陥り、ヒロシマ・ナガサキを終局とする全面的破綻という極めて特異な経験を有している。他方、長期的視点に立てば、近隣アジア諸地域との多様な交流を通じて重層的な文化圏を形成してきた歴史をも有している。そのことを踏まえるならば、破滅的核戦争に突入しかねない現在の危機を回避するための積極的な外交的イニシアチブを発揮する知恵を自らの歴史の中に見出すことができるはずなのではないだろうか。