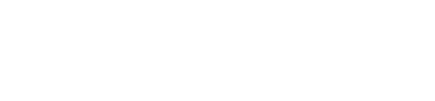憲法審査会 | 平和フォーラム
2025年12月17日
憲法審査会レポートNo.66
臨時国会が閉会、改憲機運高まらず
12月17日、今臨時国会の会期末を迎えました。同日、衆参ともに憲法審査会を短時間だけ開催し、閉会にあたっての手続き処理(付託された請願(署名)の取り扱い審査など)を行い、終了しています。
高市政権成立にあたっての自民・維新の「連立合意」に盛り込まれた両党による「条文起草協議会」は発足したものの、両党の主張が噛み合っていない状況があります。衆参憲法審査会の下への「条文起草委員会」設置に関しては、幹事懇談会での提案や自由討議での発言にとどまり、正式な議題にもなっていません。
自民・維新などの改憲政党・会派がこの間手を変え品を変え、さまざまな策動を続けてきましたが、世論はいたって冷静です。しかし、保守層を繋ぎとめるために、来年以降も「改憲実現」を旗印としていくことが予想され、引き続きの警戒・注視が必要です。
【参考】
自維政権下の憲法論議 改正急ぐ理由見当たらぬ
https://mainichi.jp/articles/20251216/ddm/005/070/076000c
2025年12月17日(水)第219回国会(臨時会)
第4回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=56067
※「はじめから再生」をクリックしてください
2025年12月17日(水)第219回国会(臨時会)
第2回 参議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
2025年12月05日
憲法審査会レポートNo.65
12月4日、衆院憲法審査会では自由討議が行われ、自民・維新は憲法審査会の下に「条文起草委員会」を設置することを主張しましたが、立憲・れいわ・共産は反対を表明、与野党で設置の合意が得られる状況にはありません。
12月17日が今臨時国会の会期末です。補正予算審議などもあることから、衆参ともに憲法審査会の実質的な開催機会も少ないものとみられ、今国会ではこれ以上の大きな動きはないものと思われます。
2025年12月4日(木)第219回国会(臨時会)
第3回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=56022
【マスコミ報道から】
衆院憲法審 憲法改正 条文案起草の小委員会設置めぐり意見交換
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014993781000
自民、起草委設置へ理解求める 立民は否定的―衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025120400120&g=pol
遠い憲法審の「起草委」設置 自民「合意を得られる状況ではない」
https://digital.asahi.com/articles/ASTD42SLCTD4UTFK00NM.html
「安全」巡る認識の違い表面化 衆院憲法審査会 緊急事態条項新設に立民は反対姿勢堅持
https://www.sankei.com/article/20251204-E4FL6I7SVVOEJASJIWSYEZYZ4M/
【速報】同性婚容認へ改憲提起 自民党の中谷氏「不利益解消」
https://www.47news.jp/13548764.html
憲法審査会 条文案作りに着手する段階だ
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20251205-GYT1T00052/
【傍聴者の感想】
きょうは自由討議の形で、各党の委員が発言時間いっぱい持論を展開しました。
いわゆる「お気持ち表明」なのではないかと感じるような、それぞれが一方的に話しているような印象を覚えました。
また、「いつまでも同じことを繰り返していてはだめだ」「議論は尽くされた」と改憲ありきで発言する議員もいますが、憲法は国のあり方を示し、権力を「法の支配」で縛る国の最高法規です。落ち着いた環境で冷静な議論が必要ですし、少数会派の意見を封じてはいけません。
何よりも私たち市民は憲法を変えるべきだとは思っていません。それよりも物価高対策や社会保障の充実など生活に密接に関わる課題の解決に尽力してほしいものです。
傍聴券を手配していただいた議員の秘書の方から「今日は傍聴に小学生も参加する」と聞いていましたが、きっと小学生は憲法審査会を傍聴して「ぽかーん」としたと思います。発言内容が難しいというよりも、一方的に主張し、話がかみ合わない様子は、「会議」のイメージとかけ離れているからです。
そもそも、憲法で世の中を、世界を良くしたいという発想からの改憲議論ではなく、世界情勢が危険だから憲法を変えないといけないという発想自体が、ナンセンスで本末転倒です。どうしたら世界が良くなるか、そのために努力しましょうと憲法前文にも書かれています。
改憲ありきの委員の姿勢や発言は、努力すべき方法や方向を誤っているように見受けられました。
【国会議員から】山花郁夫さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会筆頭幹事)
 いうまでもなく憲法改正のためには、衆参両院の2/3以上の賛成が必要です。
いうまでもなく憲法改正のためには、衆参両院の2/3以上の賛成が必要です。
近年与党だけで2/3を占めるということがありましたが、戦後80年間の歴史をみると、これは歴史的には稀有な事態といえます。一般的には野党第一党が賛成していなければ両院での2/3の合意形成は難しいといえます。法律と違って、憲法というのは、どんな考え方の内閣であっても、どの政党が政権を担っても、そのルールの下に政治を行うという、いわば与野党に共通のルールだけに、2/3要件というのは、与野党一致で共通認識が形成されることが求められているものといえます。
国民投票法を制定するに際しては、このような事情を意識しながら立案したものでした。すなわち、将来的に憲法の改正が発議されることがあるとすれば、与党・野党の垣根なく共通認識を形成して、成案を作成していくというプロセスが重要になるということを認識し、その手続法である憲法改正国民投票法も同様に、与野党で真摯な議論を行って共通認識を形成し、成案を得ていこうという努力がなされました。衆議院憲法審査特別委員会において、最終的には不本意な形での採決となりましたが、ギリギリまでその努力がなされたもので、船田会長代理はその当事者でもあられます。
国民投票法成立当時から、国民投票の賛否の勧誘にかかわるCM規制について議論がありました。私たちとしては、民放連が制定当時と異なる答弁が後になされたことから、問題意識を持っていたところです。
制定から時がたち、テレビ・ラジオはオールドメディアとよばれるようになり、テレビ・ラジオよりもSNSのほうが社会的影響力は大きくなっており、偽・誤情報対策については当審査会でも議論してきました。さらに、諸外国において選挙の際の外国からの干渉などの問題も、当審査会でも先日、衆議院の海外調査(枝野団長)において、報告を受けたところです。
広報協議会については幹事懇談会で議論が進んでいますが、国民投票法についてはその他にも議論すべき論点があると考えています。この点については、前回改正時に附則4条に盛り込まれているテーマもあります。附則4条には、「法律の施行後3年を目途に、……」「検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」ことになっているところ、すでに3年以上を経過しており、立憲民主党としては今後の審査会でも附則に規定されたことについて重点的に議論がなされるべきと考えます。
前回改正の時には、私と新藤筆頭との間で相当な時間をかけて折衝を行いました。当時も公選法並びの改正という比較的技術的な内容の改正の提案がなされていました。CM規制等の問題も同じ国民投票法の改正案であることから、採決を行うのであれば立憲民主党の問題意識を盛り込めるものは改正法に編入してほしいという当方の立場との乖離を埋めることに相当なエネルギーを費やしたことが思い出されます。最終的には附則に落とし込むことにより、双方の合意を形成することができました。対立した形での採決とならなかったことについては当時の新藤筆頭幹事にも敬意を表したいと思います。
ただ、その後に附則で規定した事項についての議論が加速化することはなかったというのは残念に思います。
国民投票法は手続について定めるものですが、どの党の案がベースになったものだという色がついてしまうと、「改憲派に有利なルールだ」とか、「護憲派に有利なルールだ」というレッテルを張られ、手続の正当性に疑義が生じるおそれがあります。その意味で、現在も立憲民主党として法案の形で党内的には整理しているところですが、これを対案的に提出しようというのではなく、論点についての考え方を提起しつつ、各党各会派にご理解をいただいてコンセンサスを作っていきたいと考えています。
将来的に多くの与野党のコンセンサスが形成されて「憲法改正が発議された」という事態を想定し、国民投票での過半数を視野に入れると、どの党の案がベースになったという色がつかないことが大事だと思います。
かつて、中山太郎憲法調査会長(当時)と、ルクセンブルクに国民投票の視察に行ったことがあります。EU憲法批准の可否に関する国民投票でした。議会では圧倒的多数が賛成していたにもかかわらず、国民投票の結果は僅差のものでした。政党色や内閣に対する審判のような色がつくと、思わぬ結果となることを中山先生と語り合ったことが思い出されます。
こうした事例などの教訓として、国民投票での過半数を視野に入れると、発議される憲法改正案はどこの党の主張であったというようなことが希釈されていることが必要で、起草委員会というアイデアはこのような文脈で語られてきたはずです。
現状はそのアイデアになじむ状態ではないというだけでなく、憲法改正の「わが党案」のようなものを主張されている党があるとすれば、これまでの憲法調査会以来の知見をふまえたものとはいえず、国民投票での過半数獲得の阻害要因となることは指摘しておきたいと思います。
なお、議員任期延長に関連して、総選挙を全面的に停止しなければならない立法事実を確認できない旨申し上げてまいりました。
少し角度を変えて説明したいと思います。
公立中学校で「男子生徒の髪型は丸刈りでなければならない」という校則があったとします。法の下の平等という観点からすると、この校則を違憲・無効なものであるとして、男子学生の髪型についての規制をなくす、というのが適切な是正策と考えられます。
これに対して、「女子生徒の髪型も丸刈りでなければならない」という校則を新たに作成して、男子学生・女子学生間の平等を解消するような方策をとるべきでないことは言うまでもありません。人権を侵害する方法で平等を実現することは「不正義を倍増」することにほかならないからです。
そこで、大規模災害の場合です。東日本大震災のようなケースでも、8割強の地域は選挙の執行が可能でした。1割強の地域で選挙の執行が困難であることを理由として衆議院選挙を全面的に不能だと論じることは、比率において上回る地域の選挙権行使の機会を停止することにより「平等」を確保しようとするもので、女子学生を丸刈りにするのと同じように投票の権利を侵害・制限する方法で平等を実現する方策といえます。繰延投票等の方法を活用することが適切な解決方法だということを改めて申し上げて発言といたします。
(憲法審査会での発言から)
2025年11月28日
憲法審査会レポートNo.64
11月26日、今臨時国会はじめての参院憲法審査会が開催されました。このなかで日本維新の会が憲法審査会の下に条文起草委員会を設置する提案をし、これに国民民主党から賛意が表明されたものの、自民党は積極的な反応を示しませんでした。
いっぽう、27日に行われた衆院憲法審査会幹事懇談会では、船田元・与党筆頭幹事が憲法審査会への条文起草委員会設置を提案、維新が同調、立憲・共産・れいわが反対しました。
これら「憲法審査会への条文起草委員会設置」の提案は自民・維新の「連立合意」に基づくものですが、自民党の衆参での対応には温度差がすでに表れています。
また、自民・維新両党による「条文起草協議会」の場においても、改憲に前のめりの維新の姿勢が際立ってきています。
【参考】
自民、条文起草委を提起 衆院憲法審査会、立民は反対
https://www.47news.jp/13514189.html
自民、条文起草委を提案 衆院憲法審、立民「時期尚早」
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025112700573&g=pol
維新、憲法9条2項削除・国防軍を説明 自民「いきなりそこまでは」
https://digital.asahi.com/articles/ASTCW3J38TCWUTFK009M.html
2025年11月26日(水)第219回国会(臨時会)
第1回 参議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8753
【マスコミ報道から】
参議院憲法審査会 今国会で初の討議 憲法の考え方で意見交わす
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014986851000
維新、条文起草委を提案 参院憲法審、野党は反発
https://news.jp/i/1366324694204269207
条文起草委設置で足並みそろわぬ与党 今国会初の参院憲法審、「周回遅れ」挽回なるか
https://www.sankei.com/article/20251126-CECNUXJY4JIGHDPPWQPKIJWVLY/
臨時国会での改憲論議、自民なぜ抑え気味 初の参院憲法審査会から
https://digital.asahi.com/articles/ASTCV323DTCVUTFK00KM.html
【傍聴者の感想】
高市政権発足後、初の参議院憲法審査会が開催されました。今夏の参院選を経て会派の構成や委員も変わりました。初開催だからということか、各会派代表が「憲法に対する考え方」を表明し、その後委員の自由な発言を時間終了まで行いました。
各会派の発言は概ねこれまでの主張を繰り返したもので、特に新しい課題提起はなかったように思います。参議院の緊急集会を積極的に活用する方向性は各会派共通するなど、衆院との違いも従来の論調が継続していると思いました。自民と維新の連立合意に触れた発言がいくつもあったのが、今までとの違いでしょうか。
初めて参加した参政党の発言が注目されましたが、「憲法は一から作り直す創憲」「憲法は権力を縛るものではなく、国のあり方を示すもの」「今の憲法には伝統的な文化や価値が記載されていない」「日本は古来から憲法を自主的に作ってきた(聖徳太子など?)のであって自分たちで作ることが大事」など、この間にマスコミなどでも報道されていた主張でした。
委員の自由討議でも参政党の委員の発言がありましたが、「子どもの権利を守らなければならない。長時間保育は子供の情緒をゆがめている。そのために3歳までは家庭で育てることを定めるべき。憲法で、『子供は国の宝』と明記すべき」との主張を展開。批判の仕方は幾通りも思いつきますが、問題はこのような発言が現代の国会において堂々となされることを可能にしている私たちの社会のあり様でしょう。私たちの日常において、分断と対立は乗り越えつつ、批判すべきことはきちんと批判するということが、今まで以上に大切なってくるのだと感じました。
【国会議員から】吉田忠智さん(立憲民主党・参議院議員/憲法審査会筆頭幹事)
 1.戦後80年と日本国憲法の真価
1.戦後80年と日本国憲法の真価
今年は戦後80年ですが、かつての全体主義と軍国主義がもたらした世界史にも例のない甚大な戦争の惨禍の反省に基づき制定され、今日までの我が国の発展の礎となった日本国憲法の真価をしっかりと正当に評価しなければならないと考えます。
日本国憲法は、世界唯一の平和主義を掲げ、世界屈指の人権法典にして優れた民主制度を定めたものであり、私ども会派はこの日本国憲法を守り活かしていくための議論、すなわち、良識の府にふさわしい、法の支配と立憲主義、そして、憲法の基本原理に基づく憲法論議をこの審査会で求めて参ります。
2.憲法審で議論すべき事項
さて、本日は、今後の本審査会において議論すべき三つの事項について指摘したいと思います。
(1)緊急集会
一つは、参議院の緊急集会に関する議論です。参院憲法審では、2023年常会で緊急集会の制度、24年常会で災害時等の緊急集会の運用について大変充実した議論を行ってきました。今後は、緊急集会のあるべき機能強化などに関する論点を更に議論し、具体的な制度改善に結びつける必要があります。
特に、本年の常会で自民党の中西筆頭幹事が指摘されたように、参議院の「都道府県選挙区の合区」が緊急集会の制度趣旨に合致するものか検討が必要と考えます。この点、昨年6月の選挙制度専門委員会の報告書において、二院制における参議院の機能・役割として、災害対応について「緊急集会の機能の充実強化」が明記され、その答申を受けた参議院改革協議会報告が本年6月に纏められております。
今後は、改革協議会と本審査会との連携が極めて重要であり、まずは、この間の経緯等を聴取し、憲法問題を担当する憲法審査会の責任を果たしていく必要があると考えます。
なお、緊急集会を巡っては、任期延長改憲の根拠として、「総選挙の実施が可能な平時の制度であり、開催期限は70日間限定であり、二院制の例外制度としてその権能は大きく制約される」といった主張が衆院憲法審で任期延長改憲を主張する方々によってなされてきました。
ところが、参院憲法審では、自民、公明、そしてご勇退された大塚耕平先生などが会派代表意見において、衆議院の任期延長改憲を主張する方々とは異なる緊急集会に関する正しい見解を述べられてきました。昨年8月の自民党の党見解のWG報告にはそうした良識の府の見識が具体的に示され、かつ、本年の常会でも佐藤筆頭幹事を先頭に任期延長改憲を主張する方々の見解に汲みしない緊急集会の正しい主張がなされたことに敬意を表する次第です。
特に、佐藤筆頭幹事の質問による川崎参院法制局長の答弁によって、予算や条約などの衆議院の優越事項も緊急集会の議案となることが明確に確認されたことは非常に重要です。
こうした、参院憲法審の論戦にもかかわらず、衆院憲法審では先の常会の会期末に緊急集会の誤った見解に基づく任期延長改憲の骨子案の議論が行われたことは誠に遺憾です。
ただ、その中で、「70日間は緊急集会の活動期間を厳格に限定するものではない」という見解が初めて示されています。この点、任期延長改憲の「選挙困難事態」の定義には70日間限定説に基づく「70日を超えて」という「長期性の要件」があり、この改憲骨子案の見解は、任期延長改憲の論拠の根幹の崩壊を意味するものと考えます。
先の自民・維新の連立合意には、任期延長の改憲条文の来年の常会提出等が記されています。緊急集会を巡る見解が衆参で深刻に分裂し、任期延長改憲を主張する方々の見解の正当性そのものが崩壊する中で、衆院での改憲条文の提出など断じて許されません。ましてや、そのための、衆参憲法審査会での条文起草委員会の設置など断じて許されようがないことを明確に指摘いたします。
(2)国会法102条の6に基づく憲法違反問題の調査審議
次に、国会法102条6が定める憲法審査会の法的な任務である憲法違反問題などの調査審議の実行も極めて重要であります。
先に、高市総理による存立危機事態条項の台湾海峡有事での適用答弁が日中の国際問題に至っていますが、そもそも、安倍政権の集団的自衛権行使は昭和47年政府見解の「外国の武力攻撃」という文言の曲解等によってなされた憲法違反であることが、2015年の安保国会では濱田邦夫元最高裁判事や宮﨑礼壹元内閣法制局長官らによって陳述されています。
また、それが故に、武力行使の新三要件が歯止めのない・無限定なものであることも国会質疑で論証されていますが、日本による米国のための集団的自衛権行使を法的に免責した日米安保条約3条など日米同盟との関係も含め、国家による戦争行為の発動である存立危機事態条項の憲法問題について、本審査会で冷静にしっかりと調査審議を行う必要があります。
なお、我が会派は自民・維新の連立合意にある、あらゆる武力行使を可能にしてしまう憲法9条そのものの改憲には明確に反対をいたします。
合わせて、多くの高裁で違憲判決が出ている同性婚禁止、あるいは、選択的夫婦別姓、さらには、臨時国会の召集義務違反など、国民の人権や民主主義の在り方に直結する重要な憲法問題もしっかりと審議する必要があります。
(3)国民投票法
更には、国民投票法について、附則4条が求めているテレビやネットのCM規制、ネット上のフェイク情報の対処などについて、引き続き議論を深めていく必要があります。
特に、インターネットについては、いわゆるフィルターバブル・システムや、再生回数稼ぎのビジネスモデルなど、「ネット社会の民主主義の在り方」という根本的な視座に立った検証が必要と考えます。
3.最後に
以上、良識の府にふさわしい、立憲主義に基づく憲法論議を求めて私の意見といたします。
(憲法審査会での発言から)
2025年11月21日
憲法審査会レポートNo.63
11月20日、今臨時国会2回目となる衆院憲法審査会が開催され、イギリス・ドイツ・EU本部の国民投票制度の調査団派遣(9月)の報告があり、偽情報対策などについて討議しました。なお、来週27日の幹事懇談会には船田元・与党筆頭幹事が、自民・維新の「連立合意」に基づき、憲法審査会への条文起草委員会設置を提案する可能性があります。
参院については幹事懇談会が19日に行われ、26日に今国会初の参院憲法審査会開催で合意しています。
【参考】
衆院憲法審、20日開催へ 偽情報対策の海外事例を報告
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA132Z30T11C25A1000000/
参院憲法審、26日に初開催
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025111900475&g=pol
2025年11月20日(木) 第219回国会(臨時会)
第2回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55984
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
衆院憲法審 国民投票時の偽情報対策に規制の導入検討すべき
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014981811000
自・立、事業者規制の強化主張 衆院憲法審、偽情報対策巡り討議
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025112000129&g=pol
与野党、偽情報巡り議論 衆院憲法審、高市政権で初
https://www.47news.jp/13480892.html
※タイトルには「高市政権で初」とありますが、本文にあるように「初の討議」です(開催自体は2回目)。
高市政権で初の衆院憲法審、与野党が偽情報やフェイクニュース対策めぐり議論
https://www.sankei.com/article/20251120-JVPLLFSR2BKORPQGR6HZKBJ4QY/
【傍聴者の感想】
衆議院憲法審査会が11月20日に開催され、会長は枝野幸男さん(立民)から武正公一さん(立民)になったほか、委員の顔ぶれも若干変わる新たな体制で始まりました。
さて、今回の審査会ではイギリス、EU及びドイツの憲法及び国民投票制度について、現地に赴いた調査報告にたいする各委員から質問や意見を述べ合う自由討議が行われました。
調査を行った議員団は3名で、調査団長の枝野さんが、調査の主たるテーマである「国民投票における偽情報対策及び外国勢力による介入への対応、政治広告規制」について各国の状況を報告し、会長代理の船田元さん(自民)と武正さんが補足の報告を行いました。
偽情報やSNSの拡散情報、政治広告による投票行動への影響、またそれらを規制することと表現の自由のバランスをどのように取りうるか、各委員の質問や意見が集中していましたが、一方で、行政側が一方的に新聞社をフェイク報道呼ばわりした事例や、特定野党を誹謗中傷したことで問題となったSNSアカウント「Dappi」と自民党との関係に触れたうえで、国民投票広報協議会がきちんと自浄作用を含めて機能させることができるのかと疑問を呈する意見が出ていました。それはその通りで、いくらSNS規制と表現の自由のバランスをとったすばらしい制度設計ができたとしても、肝心かなめの広報協議会が偏重したりフェイクしたりしては、お話にならないのでもっともなことでしょう。
その他一部委員からは憲法改正を前提とした議論はするなとの意見もありました。この間の永田町政治の状況を見ていると、どうも憲法の枠内で政治の運営を行うという立憲主義が十分に機能していないきらいがあるようです。「憲法について広範かつ総合的に調査を行う」ことも大切なのでしょうが、こうした政治状況の調査・分析も憲法審査会でされてはいかがかと思いました。
2025年11月14日
憲法審査会レポートNo.62
自・維、改憲に向けて動き強める
自民党と日本維新の会は13日、「連立合意」に基づいて改憲条文起草協議会を開催しました。まずは両党レベルで緊急事態条項や憲法9条の改憲条文案作成をめざすとともに、衆参憲法審査会への「条文起草委員会」設置提案を行うなどするもようです。
高市首相は4日の衆院本会議の代表質問で、内閣が国会に改憲案を提出することが可能との見解を示すも、12日の参院予算委員会では「高市内閣から提出することは考えていない」と述べています。
なお、13日に行われた衆院憲法審査会幹事懇談会で、20日に審査会を開催することが合意されています。
【マスコミ報道から】
自民と維新、9条改正へ議論開始 連立合意通りの進展見通せず
https://www.47news.jp/13450303.html
衆院憲法審20日に開催へ 与野党で合意 高市政権下で初の実質討議
https://www.sankei.com/article/20251113-H6YPH2AODJO3VLLGRE3LELIVMI/
「内閣も改憲案提出可能」高市首相が断言した政治的な理由とは… 持論が口に出てしまい危うさは加速する
https://www.tokyo-np.co.jp/article/449090
2025年10月24日
憲法審査会レポートNo.61
高市政権成立、改憲発議に意欲示す
10月21日、高市早苗・衆議院議員が首相に就任しました。今回公明党が政権から離脱、そのかわりに日本維新の会から「連立」と称する閣外協力を取り付けましたが、その際交わした「連立政権合意書」には憲法9条改正と緊急事態条項創設に向けた両党による条文起草協議会設置、「国旗損壊罪」や「スパイ防止法」制定などの項目が含まれています。
同日、衆議院憲法審査会が開催され、枝野幸男会長が辞任(予算委員会委員長に就任)、このかん野党筆頭理事を務めてきた武正公一・衆議院議員があらたに会長に就任しました。
高市首相はもとより「憲法改正」「非核三原則見直し」などを主張してきた極右傾向の濃い人物です。今後の改憲をめぐる動向に対しては、強い警戒と注視が必要です。
【マスコミ報道から】
自維 連立政権合意書 要旨=2025年10月24日更新=
https://www.jiji.com/jc/v8?id=20251021jiirenritu
“▽日本維新の会の提言「21世紀の国防構想と憲法改正」を踏まえ、憲法9条改正に関する両党の条文起草協議会を設置する。設置時期は、25年臨時国会中とする。”
“▽緊急事態条項(国会機能維持および緊急政令)について憲法改正を実現すべく、25年臨時国会中に両党の条文起草協議会を設置し、26年度中に条文案の国会提出を目指す。”
2025年10月21日(火)第219回国会(臨時会)
第1回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55952
【会議の内容】
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/219-10-21.htm
2025年06月20日
憲法審査会レポートNo.60
6月18日の参議院憲法審査会は、国民投票法等についての意見交換が行われました。しかし、確認できる限りではいっさいニュース記事の配信がありません。国会会期末が迫り、また同日戦後初の「衆院財務金融委員長解任」があったとは言え、これは驚きです。改憲に向けた「機運」が相当後退していることの表れでしょうか。
19日には衆院憲法審査会幹事懇談会のみ開催されました。
なお、20日は衆参ともに憲法審査会が行われますが、これは閉会にあたっての手続きのためで、それぞれ数分で終了します。
【追記】20日の参議院憲法審査会開催はとりやめになりました。
2025年6月18日(水)第217回国会(常会)
第6回 参議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8629
【主な発言項目】
https://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/keika/hatsugen_217.html#d6_hatsugen
2025年06月13日
憲法審査会レポート No.59
6月12日、衆院憲法審査会に先立って行われた幹事会に対し、改憲推進5会派が任期延長に関する改憲骨子案を提出しました。ただし、憲法審査会への提出ではないため、骨子案の内容は議事録に残りません。
2025年6月12日(木) 第217回国会(常会)
第9回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55864
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
自民など5党派が改憲骨子案 議員任期延長で―衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025061200889&g=pol
災害やテロなどなどの緊急時に国会議員の任期延長、改憲骨子案を初提示…自民など5党派
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250612/k10014833321000.html
“選挙困難な緊急時は議員任期を延長” 自民など改憲骨子案
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250612/k10014833321000.html
改憲5党派、議員任期延長の改憲骨子案提示 憲法審では取り上げず
https://digital.asahi.com/articles/AST6D3Q05T6DUTFK009M.html
5党派が「議員任期延長」の改憲骨子案提示 自民内の「溝」が懸念材料 衆院憲法審幹事会
https://www.sankei.com/article/20250612-OPK6FA7GCZIVHMCZ6T2X7AVTKQ/
【傍聴者の感想】
今回は各会派の代表から今国会中の審査会の討論について総括を受け、自由討論が行われました。事前の幹事会では自民、維新、公明、国民、有志の会の5会派から改憲案の骨子が提出されたものの、自民党の総務会を経ていないなど自民党内で手続きが採られていないものとのことで、審査会に出席した議員や傍聴には配布はされませんでした。
討論では、あらためて「選挙困難事態」をめぐって意見が交わされました。自由民主党などが改憲の理由として示す「選挙困難事態」に対して、立憲民主党から「立法事実にあたらない」、日本共産党から「議員の任期延長は国民の選挙権の停止につながる」といった反論がありました。
日本維新の会からは「国民主権を具現化し、主権者である国民に判断を仰ぐためにも、国民投票の実施を」、国民民主党からは「憲法審査会の具体的成果を可視化すべき」といった意見が示され、憲法改悪に向けた一歩を踏み出したいという思惑が明白に見て取れました。
物価上昇や「コメ不足」などに象徴される、人々の苦しい生活をどう改善するかはあとまわしです。彼らの政治的思考のあり方は「国家」の下に「国民」をいかに従属させるかであり、有権者である「国民」の日々の生活の向上にはないということが強く感じられました。参院選勝利に向けたとりくみを強めたいと決意しました。
2025年06月06日
憲法審査会レポート No.58
改憲会派、9条と現実の乖離を埋める改憲を主張
6月4日の参議院憲法審査会は、改憲の是非を問う国民投票時の偽情報対策で参考人聴取が行われました。新しいデジタル環境社会の中で、偽誤情報の拡散は大型選挙の結果にも影響を及ぼしています。参考人の意見を踏まえて各会派から質疑が行われ、総合的な対策の必要性が討議されました。
翌5日の衆院憲法審査会では、憲法と現実の乖離をテーマに自由討議が行われました。立憲民主党は、滝川事件と呼ばれる思想弾圧事件を例に挙げながら、大学の自治や学問の自由など人権課題の重要性を訴えたことに対し、改憲推進派は世界の安全保障環境の緊張が高まっているとし、9条と現実の乖離を埋める改憲が主張されるなど、各会派の憲法に対する立場の違いが明らかとなりました。
2025年6月4日(水)第217回国会(常会)
第5回 参議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8593
【マスコミ報道から】
参院憲法審査会 SNSの偽情報対策などで参考人質疑
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250604/k10014825781000.html
偽情報対策、国民投票法改正を 参院憲法審で参考人質疑
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025060401073&g=pol
【傍聴者の感想】
今回は、「国民投票において、インターネット上の偽情報等への対策をどうすべきか」について、参考人3名を呼ぶ形での開催でした。
フェイクニュースは出ては消えての「いたちごっこ」で、後を絶ちません。参考人3名とも「難しい問題で…」と、口をそろえて答弁していたのが印象的でした。偽情報を発信する側がもちろん悪いのですが、被害者は速やかに情報を公開することで信頼性を獲得することが当面は必要だと述べていました。
日本は偽情報対策が諸外国に比べ遅いということです。それは参考人が指摘したように、イギリスのブレグジット(EU離脱)に関する国民投票やアメリカ大統領選挙においてネット情報が投票行動に影響を与えた2016年の事例が、2024年の東京都知事選、衆院選、兵庫県知事選に表れていることからもうかがえます。
生かすも殺すも、私たち次第です。AIなど技術が発達しうまく活用すれば生活を豊かにしてくれますが、悪意を持って用いることで社会に混乱をもたらします。ファクトチェック団体の資金不足をはじめとする総合的な対策を施すべきではありますが、「表現の自由」との兼ね合いもある一方で、十分に議論をせず拙速な判断をすることもかえって逆効果だと考えます。
直近では6月22日の東京都議選、7月の参議院選挙において何が起こるか、目が離せません。
【傍聴者の感想】
先の大戦の反省から「二度と戦争はしない」と誓った、日本国憲法が施行されてから78年が経ちました。これまで憲法改正の国民投票は一度も実施されていません。こうした中で憲法改正を国民投票にかけた際に、世論がどう動くのかはまったく読めません。
この日の参院憲法審査会では、憲法改正の是非を問う国民投票に関して、三人の参考人(北九州大学法学部・山本健人准教授、日本ファクトチェックセンター・古田大輔編集長、大阪大学社会技術共創研究センター・工藤郁子特任准教授)から意見を聴取して各会派の委員との質疑が行われました。
デジタル技術やAI機能の進歩といった新しいネット環境を介した情報流通において、私たちはかつてないほどの利便性を手に入れた一方で、偽誤情報による弊害も加速度的に悪化しています。北九州大学の山本教授からは、偽情報等の根絶や影響力の無効化はほぼ不可能としながら、①偽情報等の量・接触機会を減らす、②正確な情報やファクトチェック記事の発信により偽情報等に対抗する言論を増やす、③情報受領者(有権者)のメディア・ICTリテラシーを高める、など3つの基本的な対策の方向性が示されました。
私自身、自分のバイアスと相性が良い情報は、正しい情報と思い込みやすいことを自覚します。日本はネット社会における偽誤情報の対策が遅れていることが指摘されます。こうした対策が不十分なまま、国民投票で世論を二分するような改憲発議に踏み込むことは許されません。
この日の参院憲法審査会は、各会派の問題意識と参考人との質疑が繰り返され、これまでの改憲推進派と慎重派の対決色が薄まりました。国の最高法規である憲法の議論は、こうした落ち着いた環境の中で冷静な議論こそ必要だと感じました。
2025年6月5日(木) 第217回国会(常会)
第8回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55847
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
衆院憲法審 自民など 憲法に自衛隊の存在明記と主張
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250605/k10014826661000.html
自民、自衛隊の憲法明記を主張 立民は性別変更要件の改正要求
https://www.47news.jp/12679786.html
自衛隊明記の改憲主張 自維国、衆院憲法審で
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025060500790&g=pol
【傍聴者の感想】
今回の衆院憲法審査会は「憲法と現実の乖離」について議論されました。
各議員の発言に対して他の会派から質問が出され、それに対する回答が示されるなど、これまでの言いっ放しの討論とは様相が変わってきました。
日本は先の大戦の反省から不戦を誓ったはずです。戦後80年となる節目の年に日本を再び戦争ができる国として憲法改正をしてはならないのは当然です。
時代に合ったという意味で、憲法について考えることは必要なのかもしれません。しかし、憲法改正を行うのであれば、当然、私たち市民のための改正である必要があります。議員自身が「国民のため」と称して自分たちの考えを一方的に主張して良いとはとても思えません。
国際情勢の緊張の高まりによる9条と現実の乖離を指摘して、現実に合わせた憲法改正は本末転倒にしか思えません。二度と戦争はしないと誓ったはずです。憲法の高い理想に少しでも現実を近づける、そうした外交努力こそ今の日本には必要なのではないでしょうか。私はどうしても今回の憲法審査会を傍聴して、そのように感じてしまいました。
私はまだ数えられるほどしか傍聴をしていませんが、憲法審査会という場は、国の礎となる最高法規である憲法について、私たち市民のための議論をお願いしたいと思います。日本を戦争のない、一人ひとりが平和に豊かに暮らしていくようにするのが政治家の役目だと思います。
【国会議員から】山花郁夫さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)
 まず、学問の自由・大学の自治に関する問題です。この問題に関しては、京大事件(滝川事件)が有名です。
まず、学問の自由・大学の自治に関する問題です。この問題に関しては、京大事件(滝川事件)が有名です。
1933年、文部大臣が京都大学総長に対し、法学部の滝川幸辰教授をやめさせるように、申し入れをしたことに端を発します。
京都大学法学部教授会は、学問的研究の結果として発表された、刑法学上の所説の一部が政府の方針と一致しないという理由で、教授が退職させられるようでは、「学問の真の発達は阻害せられ、大学はその存在の理由を失うに至」るとして、反対意見を提出しましたし、京大総長もまた、文部大臣の要求には応じませんでした。
そこで、文部大臣は滝川教授を休職にしました。「休職」といっても、当時の休職というのは、事実上の免官です。
この時の文部大臣の行為が合法であったかついては、議論があります。明治憲法には学問の自由の規定がなかったわけですし、休職処分について手続的には瑕疵はなかったのかもしれません。しかし、政治権力によって、大学の教授を、その学問的所説のみの理由に基づいて、事実上免官するという行為は、学問の自由に対する侵害であったというほかありません。
京大事件などの教訓から、学問の自由を十分に保障するためには、大学の人事に関して政府が介入しないことが求められます。
最高裁も、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される」としています(東大ポポロ事件・最大判昭和38.5.22)。
ところで、菅首相(当時)は2020年秋、日本学術会議が新会員候補として推薦した候補者105人のうち安保関連法に批判的といわれた6人を除外して任命する異例の決定をしました。
この問題について、委員の「任命」は内閣総理大臣が行うのだから、任命をしないことも適法である、という見解に対して、いやいや、任命という用語が用いられているが、これは形式的任命であって、拒否はできないのだ、ということが争われています。法律制定の経緯からいって、後者が正しいと私は思うのですが、この議論は、京大事件における休職処分の適法性の問題に似ていて、そこが本質的な問題ではないように思われます。
大学の自治が保障されるべきなのは、「大学」という組織だからなのではなくて、学問の自由が保障される研究者による組織だからだとすると、学術会議という団体にも、人事権などが、政府によって干渉されないことが憲法23条によって保障されていると考えられます。
ここに、「干渉」とは、自治が認められる趣旨からすると、メンバーの解任という積極的な介入だけでなく、任命拒否も消極的な介入と評価されますから、今回の任命拒否は憲法が学問の自由を保障した趣旨に反するというべきでしょう。
なお、イギリスと異なってドイツ型の大学とは「官立大学」を基本としているため、資金提供者である国、つまり政治から介入を受けやすいことから「学問の自由」を独立した条文として規定していることに鑑みると、政府が財政民主主義や憲法15条の公務員の選定罷免権などを理由に挙げていることは適切でないと考えられます。もし財政民主主義などのほうが優越する価値であるとすると、京大事件や天皇機関説事件も正当化されかねない理屈であることは指摘しなければならないと思います。
次に、性同一性障害者の性別の特例に関する法律3条1項4号が憲法13条に違反するという最高裁大法廷決定が令和5年10月25日に出されましたが、今日現在、いまだ改正がなされていません。
第三者所有物没収事件については違憲判決から半年後に「刑事事件における第三者の所有物の没収手続に関する応急措置法」が制定され、薬事法適正配置規制は違憲判決の後1か月足らずで議員提案で適正配置条項を削除する法律が制定され、森林法分割規定は違憲判決の後1か月程度で森林法186条を削除する改正法を成立させ、平成14年9月11日に出された郵便法違憲判決は同年11月27日に改正法が成立し、在外日本人選挙権制限や国籍法違憲判決の後も半年程度で法改正がなされています。
違憲判決が出されてから1年以上放置されているというのはきわめて異例であり、早急に法改正をすることが必要であると考えます。
また、同性婚を法的に保障しないことが憲法違反であるという高裁判決が続いており、最高裁の判断も時間の問題ではないかと推測されます。同性婚に対する法的整備は喫緊の課題であると考えます。
なお、本日の「憲法と現実の乖離」というテーマで取り上げるべき課題について党内で意見を求めたところ、刑事手続上の人権については憲法に詳細な規定があるにもかかわらず人質司法になっているではないかという問題、憲法25条と生活保護の問題、労働基本権と労働組合の組織率の低下の問題、ひとしく教育を受ける権利と経済格差の問題、唯一の立法機関性と政省令委任の問題や地方自治など、枚挙にいとまがないほどの課題の提起がありました。憲法審査会は、日本国憲法および日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うことも重要な権限であります。今後、こうした課題を憲法審査会のテーマとして取り上げていただくことを各会派にお願いして発言とさせていただきます。
(憲法審査会での発言から)
【国会議員から】武正公一さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)
 国会は国権の最高機関とされながら、それが現実と乖離している点が憲法第7章財政です。
国会は国権の最高機関とされながら、それが現実と乖離している点が憲法第7章財政です。
昨年の補正予算案は1000億円の災害対策費修正、今年度予算は衆議院に回付され高額療養費の修正がされました。それぞれ立憲民主党は予算修正を求めましたが、その修正には政府の対応に時間を要することで、速やかな修正審議ができない事態が起きました。国会の議決がすみやかにおこなえるよう見直しが必要です。
この10年を振り返れば、予備費が過大に計上され、その使途の範囲を広げてきました。憲法83条「国の財政処理の権限は、国会議決に基づく」一方、予備費は事後承認です。憲法87条の「予見しがたい予算の不足に充てる」予備費の目的は、補正予算では軽微な事態や災害などの緊急事態に機動的に対応できないためでしたが。コロナ禍を契機として拡大した予備費を平時の状態に戻す必要があります。
さらに補正予算についても、国際機関への拠出金を当初予算に盛り込まず、補正予算ありきで予算計上され、前年度補正予算と新年度予算をセットで「15か月予算」といわれることは、単年度予算審議の憲法86条に反するものであります。そもそも、憲法には予備費の規定はあっても、補正予算の規定はありません。財政法29条には「経費の不足」「緊要となった経費」との補正予算の規定がありますが、常態化しているのではないでしょうか。
政府は1977年の統一見解において、「項」を新設する修正もありうる旨の立場を明らかにしましたが、「国会の予算修正は、内閣の予算提出権を損なわない範囲で可能」という限界説を維持しています。しかし、予算法律説をとれば、条理上の制約は別として、修正権に制限は存しないことになる。と芦部信義著「憲法」で述べています。
予算修正権に限界はないとすると、国会の予算審議権の充実のため米国議会を見習って国会予算局のような「予算審議に供する組織」を設けることが必要ではないでしょうか。
そして、国会の調査、立法機能の強化が必要であることは、30年ぶりの与党過半数割れに伴い、議員立法数の増加により、衆議院法制局の仕事量が増加しているため衆議院調査局や国会図書館調査及び立法考査局とともに、定員の増員や予算の充実が必要です。
なお、財政規律については、債務比率が250%を超える中、「国会に長期財政予測機関を設けること」も提言されています。こうした機関の創設とともに、憲法における予算、財政についてはより議論を深める必要があると考えます。
(憲法審査会での発言から)