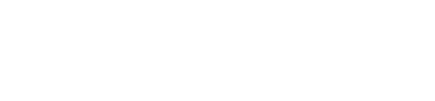2025年、平和軍縮時評
2025年05月31日
核抑止政策の現状と課題:求められる核抑止依存からの脱却
渡辺洋介
1.はじめに
ロシアによるクリミア併合(2014年)は、欧米とロシアの関係に深い亀裂を生んだ。そしてロシアによるウクライナ侵攻(2022年)がこれに続き、世界の分断は一層広がり、欧米を巻き込んだ戦争勃発への危機感が一気に高まることになった。そうした中で多くの核保有国が核抑止への依存を強め、一部の核保有国は核軍拡を進めている。また、日韓など他国の核抑止に自国の安全保障を依存する国々も、核抑止への依存をさらに強めている。核兵器の使用を前提とした核抑止政策への依存を強めることは、被爆者の思いを踏みにじる行為であるばかりでなく、誤算やミスコミュニケーションによる核兵器の使用など、様々なリスクを高める行為でもある。以下では、近年の核抑止をめぐる世界の状況を概観したうえで、本来進むべき方向性を改めて確認したい。
2.米欧分断と仏英の核兵器政策
第2次トランプ政権発足後、米国はウクライナ防衛にコミットする意思がないことが徐々に明らかになってきた。その象徴的なできごとが2025年2月末から3月初めに起きた。2025年2月28日、トランプ大統領は、ワシントンを訪れていたウクライナのゼレンスキー大統領と会談した際、米国がウクライナの安全を保障すると明確に約束せず、激しい口論となった。その4日後、米国はウクライナへの軍事支援一時停止を発表した。トランプ政権がウクライナ防衛に本気でコミットする意思がないことが明らかになり、欧州では米国は欧州防衛にもコミットしないのではないかとの懸念が広がった。そうした中、3月5日、フランスのマクロン大統領は、ロシアの脅威に対し、フランスの「核の傘」を欧州の同盟諸国に拡大する用意があると述べた(注1)。この方針は、マクロンが2020年2月の演説(注2)で初めて明らかにし、その後も繰り返し表明してきたものだ。これは、ロシアの脅威を強調し、フランスの核兵器の役割を拡大しようとする試みといえる。それが実現すれば、誤算やミスコミュニケーションによる使用を含め、核兵器が使われるリスクを増大させることになる。にもかかわらず、残念ながら、この提案に対してポーランドやバルト3国など一部の欧州同盟国から歓迎の声が上がっている。
欧州のもう一つの核兵器国である英国は2021 年以来、核抑止力の強化を進めている。同年公表された中長期的な安全保障政策の報告書「競争時代におけるグローバルな英国」(注3)において、英国は2010年に表明した核軍縮の方針を転換し、保有核弾頭数の上限を180発から260発に引き上げた。なお、英国が保有する核弾頭数について、ハンス・クリステンセンらは、2024年11月時点で225発と推定する(注4)。
その後、英国は2025年6月2日に「戦略防衛見直し2025」(注5)を発表した。同報告書は、核抑止力の運用、維持、更新を「国防の最優先事項」と位置付けており、自国の安全保障における核抑止への依存をさらに高める方針を示している。さらに、レイクンヒース英空軍基地に再び米国の核兵器を持ち込むことも計画されている。フランスと同様、英国も核抑止への依存を強めており、今後、欧州・ロシア関係がさらに悪化しないか懸念される。
3.中国の核軍拡と米ロの核兵器政策
英国に加え、残念ながら中国も核戦力強化を続けている。2024年12月18日に米国防総省が公表した報告書「中華人民共和国に関わる軍事及び安全保障上の展開2024」(注6)は、中国の保有核弾頭数を前年より100発多い600発と推定した。また、習近平国家主席は中華人民共和国建国100周年の2049年までに人民解放軍を「世界一流」の軍隊にすることを目指すと表明しており、目標達成に向けて、中国が2030 年までに運用可能な核弾頭を 1,000発以上保有すると米国防総省は予測する(一方で米国は、2025年1月の推定値で3,700発の運用可能な核弾頭を有している)(注7)。核弾頭数に関して中国政府は口を閉ざしているものの、衛星写真の分析などから、中国が核戦力を増強していることはほぼ間違いない。
他方、米ロに目を転ずると、それぞれ2024年11月に新たな核兵器政策を発表した。米国のバイデン政権は、すでに同年4月に核兵器使用指針(非公開)を改訂していたが、11月7日にその要約「米国の核兵器使用戦略に関する報告書」(注8)を連邦議会に提出した。報告書は、核兵器と非核能力による統合抑止、中国による核兵器の増強と多様化への対処、中ロ朝という核保有国3か国を同時に抑止する必要性などを強調する一方で、核弾頭数を米国の目標達成に必要な最小限のレベルに抑えるために軍備管理などを行う方針を改めて確認した。なお、中ロ朝を抑止するために米国の核弾頭数を増やす必要があるか否かについて、報告書は言及を避けた。この点について、トランプ政権は2025年5月現在、まだ方針を固めていない。
一方、ロシアも2024年11月19日に「核抑止に関するロシア連邦国家政策の基本原則(注9)を改訂した。ベラルーシにロシアの核兵器が配備されたことを受けて、必要な文言の調整を行い、ロシアのウクライナ侵攻後に起きた状況の変化をふまえ、ロシアによる「核抑止の行使」や「核兵器の使用」を招く恐れのある新たなケースを追加した。例えば、新たな軍事同盟の樹立または既存の軍事同盟の拡大による、その軍事インフラのロシア国境付近への進出や、潜在的敵対国によるロシア国境付近での大規模な軍事演習などがあれば、核抑止を行使し得るとした。これはNATOのウクライナやジョージアへの拡大やロシア国境付近へのNATO軍の展開を念頭に置き、それを核抑止によって防ぐ意図があるものと思われる。残念ながら、ロシアも核抑止への依存を強めている。
4.軍近代化を急ぐ北朝鮮
核抑止への依存を強めているのは、核兵器国ばかりではない。北東アジアでは、中国に加え、北朝鮮が核戦力を増強し、日本と韓国は米国の核抑止への依存を強めている。
北朝鮮は、日米韓の軍事力強化に対応すべく、核兵器増強と運搬手段の近代化を進めている。クリステンセンらによると、2024年7月時点で、北朝鮮は50発の核弾頭を保有していると推定されるが(注10)、その数を「幾何級数的に増やす」方針を同年9月に金正恩総書記がウラン濃縮施設を訪問した際に明らかにしている。
同時に北朝鮮は、核兵器などの運搬手段の近代化を進めるため、ミサイル発射実験を繰り返している。例えば、2024年10月31日には、固体燃料式の大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星 19 号」の、2025年1月6日には新型極超音速中距離弾道ミサイルの発射実験を行った。さらに、2025年4月25日には、核ミサイル搭載可能と見られる新型多目的駆逐艦「崔賢(チェヒョン)」(5,000トン級)を進水させ、数日後には、同艦より超音速巡航ミサイル、戦略巡航ミサイル、対艦戦術誘導兵器などの発射実験を行った。
また、北朝鮮は、ロシアと「包括的戦略パートナーシップに関する条約」(注11)と称する相互防衛条約を締結し、両国間の関係強化を図った。条約は経済・科学・文化など包括的な分野での協力を定めるとともに、第4条で「双方のうちの一方が他の一つの国家あるいは複数国家からの武力攻撃を受け、戦争状態に置かれた場合、他方は直ちに・・・利用可能なすべての手段を講じて、軍事及びその他の援助を提供する」と規定している。
5.拡大抑止を強化する日韓
一方、韓国は米核兵器で北朝鮮を抑止する態勢を強化した。米韓は「ワシントン宣言」(2023年4月26日、注12)で創設された「米韓核協議グループ」(NCG)などを通じて、米核兵器による拡大抑止を中心とした米韓同盟のさらなる強化を図った。続いて、2024年7月に両国は「朝鮮半島における核抑止及び核作戦のための米韓ガイドライン」に署名した(注13)。またNCGの第3回会合では、朝鮮半島における核兵器使用を想定した机上演習を、軍事当局間及び政策当局間でそれぞれ毎年行うことで合意した。この合意に基づいて、前者の米韓机上演習を2024年7月30日~8月1日に在韓米軍基地(平沢)で、後者を9月5日~6日に米首都ワシントンで初めて実施した。
日本もまた米国との同盟を強化した。2024年7月28日、日本と米国は、これまで官僚レベルで行ってきた日米拡大抑止協議を「拡大抑止に関する日米閣僚会合」(注14)として閣僚レベルで初めて開催した。日本は自国の安全保障を米国の核抑止に依存する方針をいっそう明確に示したのだ。
その方針を反映してか、日本は核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加にすら消極的である。岩屋毅外相は、2025年2月18日の記者会見で、同条約の第3回締約国会議への日本政府のオブザーバー参加を見送る決定をした理由を次のように説明した。
「核兵器を包括的に禁止する核兵器禁止条約は、この核抑止とは相容れず、現状におきましては、核兵器国がこれを締結する見込みはありません。そのような中で、この条約の締約国会合にオブザーバー参加することは、我が国の核抑止政策について、誤ったメッセージを与え、自らの平和と安全の確保に支障をきたす恐れがあると考えます。」(注15)
このコメントからは、米国の核抑止に依存しないと日本の安全を保障できないと思い込んでいる日本政府の本音が透けて見える。
今一度確認したいが、日本は被爆国である。原爆投下による惨禍を経験した日本は、核兵器の使用を前提とし、核使用のリスクを高める核抑止政策への依存を安易に強めるべきでない。アジア版OSCE(欧州安全保障協力機構)や北東アジア非核兵器地帯の創設に向けた努力など、核抑止への依存を減らすことができるような国際関係構築のために日本は真剣な外交努力を続けるべきである。
注1 フランス大統領府HP
https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2025/03/05/address-to-the-french-people
注2 フランス大統領府HP
https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/02/07/speech-of-the-president-of-the-republic-on-the-defense-and-deterrence-strategy
注3 英国政府HP
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60644e4bd3bf7f0c91eababd/Global_Britain_in_a_Competitive_Age-_the_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
注4 原子力科学者会報HP
https://thebulletin.org/premium/2024-11/united-kingdom-nuclear-weapons-2024/
注5 英国政府HP
https://www.gov.uk/government/publications/the-strategic-defence-review-2025-making-britain-safer-secure-at-home-strong-abroad
注6 米国防総省HP
https://media.defense.gov/2024/Dec/18/2003615520/-1/-1/0/MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2024.PDF
注7 原子力科学者会報HP
https://thebulletin.org/premium/2025-01/united-states-nuclear-weapons-2025/
注8 米国防総省HP
https://media.defense.gov/2024/Nov/15/2003584623/-1/-1/1/REPORT-ON-THE-NUCLEAR-EMPLOYMENT-STRATEGY-OF-THE-UNITED-STATES.PDF
注9 ロシア外務省HP
https://mid.ru/en/foreign_policy/international_safety/regprla/1434131/
注10 原子力科学者会報HP
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/00963402.2024.2365013?needAccess=true
注11 スプートニクHP
https://sputnikglobe.com/20240620/full-text-of-russia-north-korea-strategic-agreement–1119035258.html
注12 米ホワイトハウスHP
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/26/washington-declaration-2/
注13 米ホワイトハウスHP
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/11/joint-statement-by-president-joseph-r-biden-of-the-united-states-of-america-and-president-yoon-suk-yeol-of-the-republic-of-korea-on-u-s-rok-guidelines-for-nuclear-deterrence-and-nuclear-operations-o/
注14 日本外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100704441.pdf
注15 日本外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaikenit_000001_00062.html