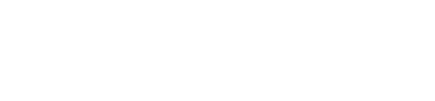憲法審査会レポート、2025年
2025年04月11日
憲法審査会レポート No.51
2025年4月10日(木) 第217回国会(常会)
第4回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55685
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
衆院憲法審 憲法改正是非問う国民投票“偽情報拡散 対応必要”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250410/k10014775691000.html
自民、偽情報「罰則が論点」 国民投票巡り衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025041000838&g=pol
【参考】
【憲法審査会】ネットの適正利用、フェイクニュース対策について。
https://yamahanaikuo.com/20250410-k/
“偽・誤情報によって民主的なプロセスが歪められることは立憲民主制にとって脅威といっていいでしょう。
しかし、ある情報を偽である、誤っていると国家が判定することについては慎重であるべきとも考えられます。学問の自由に関するものですが、天皇機関説事件というのは、国家が特定の学説を「誤っている」として排斥を始めたことに端を発しています。”
【傍聴者の感想】
今回のテーマは、「国民投票法におけるネットの適正利用、特にフェイクニュース対策」でした。
AIを用いて個人の情報をプロファイリングすることやSNS等にフェイクニュースが拡散することで、私たちの言論空間において意見が極端化し、選挙の公正の観点からいえば言論環境の混沌化によって選挙権者が適切に選挙権を行使できるか、選挙結果や民主主義に多大な影響を与える懸念が生じるといった参考人の見解から話されました。
フェイクニュースによって選挙結果が左右されたり、世論形成に影響が出た事例としては、昨年の兵庫県知事選が最も端的な例でしょう。その中で、何が真実で何がフェイクなのかを見極めることは至難の業だといえます。言論の自由、表現の自由は順守されてしかるべきですが、だからといってデマや偽の情報を垂れ流すことで人々を混乱に陥れたり誹謗中傷するような事態は許されません。国民投票の場に限らず、フェイクニュースを見つけ次第それを規制し拡散されるのを防ぐことが重要だと思います。また、日進月歩で発達する情報通信技術に対応し、私たちはリテラシー教育を受け情報を的確に判断し批判する能力を備えていかねばなりません。
インターネットの出現によって、情報の発信は個人でもたやすく行うことができますが、それだけに情報の正確性、迅速性、客観性、公平性、信頼性を担保することは、マスメディアはもちろん私たち一般市民にも求められています。
国立国会図書館からの調査報告書では、諸外国・地域からのフェイクニュース対策について報告されましたが、有志の会からは公職選挙法といった現行法だけではフェイクニュースの規制は不十分との意見が出ました。一方で、共産党やれいわ新選組からの発言で、罰則規定や規制強化によって、国家権力による情報統制や改憲に有利な意見が多数派を占めることで恣意的な判断がなされる等のリスクもあり、より徹底した議論と検証が必要ではないかと感じました。
最後に、日本維新の会等から「外国勢力」からのサイバー攻撃という発言がしきりに出ていたのを、違和感を持って聴いていたことを付け加えておきます。
【国会議員から】岡田悟さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)
 国民投票におけるフェイクニュース対策について、私どもの考えを申し上げます。
国民投票におけるフェイクニュース対策について、私どもの考えを申し上げます。
昨今の選挙では、SNS等において、虚偽情報や個人の誹謗中傷が大規模に拡散され、選挙結果を左右していると言わざるを得ない状況が生じています。また、諸外国では、自国に外交上有利となるよう、SNS等での投稿を組織的に行うことで、他国の世論形成に影響を及ぼそうとする動きがあります。
なお、今国会では、選挙戦でのポスターへの品位を求める公職選挙法の改正が実現をしました。SNS等の規制も議論となりましたが、附則によって、今後必要な措置を講ずるものとされました。選挙や政治活動でSNS等を単純に規制することは、表現の自由や政治活動の自由等を制限しかねないため、慎重な検討が求められているものと理解しています。
さて、私は、昨年十月の総選挙で兵庫7区から立候補をし、比例近畿ブロックで当選をしましたが、その直後、十一月に兵庫県知事選挙が行われました。選挙期間中や、その前後における齋藤元彦兵庫県知事による県職員へのパワハラ疑惑等の公益通報をめぐる混乱は、皆様もよく御存じのとおりと思います。とりわけ選挙戦においては、一連の問題の告発者の方や、この問題を追及していた元県議会議員の方にまつわる虚偽情報、誹謗中傷がSNSや動画投稿サイト等を通じて広く拡散をされました。
自ら命を絶たれた告発者の方は、個人であるにもかかわらず誹謗中傷にさらされ、元県議会議員の方もまた、今年一月に亡くなりました。自殺と見られています。元県議会議員の方は、生前、SNS等に端を発した誹謗中傷に大変苦慮していると私の知人に打ち明けていました。
そして、これらの情報源には、日本維新の会に所属をしていた別の県議会議員が立花孝志氏に提供した文書が含まれていました。選挙で選ばれた公職にある者がフェイクニュースの情報源となった事実は、極めて深刻に受け止めなくてはなりません。
では、こうした深刻な状況の中、憲法改正の国民投票を適切に行うことが可能でしょうか。これまでの憲法審での議論を踏まえつつ、その方法とルール作りについて検討をしました。
憲法審ではこれまで、国民投票広報協議会がファクトチェックに関与する手法が提案をされてきました。他方、広報協議会によるファクトチェックは、公権力による表現の自由への過度な介入になり得るとの懸念も示されてきました。これを踏まえれば、いかに虚偽情報であろうとも、脅迫や人命に関わるデマなど、犯罪となるものを除けば、これを制限したり削除したりすることは、実際には困難です。
そこで、特に大きく拡散をされ、世論に与える影響が大きい投稿等について、SNS事業者から情報提供を受け、広報協議会が付随的情報提供を行うといった形が考えられます。拡散された虚偽の投稿に対して広報協議会が把握している事実は何々ですなどの文言を表示することで、有権者へ注意を促します。表現の自由への過度な介入を回避しつつ、有権者により正確な情報をお示しをするとすれば、この程度が限界ではないでしょうか。
また、昨今の選挙戦では、いわゆるアテンションエコノミーを利用した収益化、SNS等で金銭を支払って虚偽情報や誹謗中傷を拡散させることが問題化しています。兵庫県知事選挙においては、業務のクラウドソーシングを仲介するサイト、クラウドワークスを通じて、事実ではないが、より感情に訴えやすいセンセーショナルな内容の切り抜き動画を作成する業務が発注され、受注者は自身の政治信条とは無関係に動画を作成して金銭を受け取っていたことが明らかになっています。これは公職選挙法をめぐる議論でも論点となっていますが、国民投票でのこうした収益化は、罰則を設けるなどして厳しく禁止をするべきでしょう。
もっとも、これらの方法でフェイクニュースの問題が十分に解決をできるとは考えておりません。虚偽情報の拡散のスピードと、これが定着をしてから説明を尽くして誤解を解くことの困難さは、国内外の多くの専門家が指摘をしているところですし、私自身も日々地元で経験をしています。
SNS等で既に生じているこれらの問題については、後ほど米山隆一委員からお話をいただきます。
また、縷々申し述べました国民投票の公平及び公正さを確保する方法を検討する中で、例えば、広報協議会とファクトチェック機関との連携の在り方、そして広報協議会とSNS事業者との連携の在り方など、より検討を深めるべき論点があるものと考えます。そのため、今後は、専門家やSNS事業者を参考人として招致をし、意見を伺う機会を設けることが適当であると考えます。
(憲法審査会での発言から)
【国会議員から】米山隆一さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)
 私は、憲法投票における様々な広報協議会のようなファクトチェック機関等を前提とした上で、その実施に先立って、先ず、先ほど法制局からも話のあった通常の言論空間における健全性の確立の必要性について申し上げたいと思います。
私は、憲法投票における様々な広報協議会のようなファクトチェック機関等を前提とした上で、その実施に先立って、先ず、先ほど法制局からも話のあった通常の言論空間における健全性の確立の必要性について申し上げたいと思います。
現在のSNS上の言論空間は、偽情報や誹謗中傷があふれております。2020年にプロレスラーの木村花さんがネット上の誹謗中傷が原因で命を絶ち、2022年に侮辱罪の法定刑を「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」とする厳罰化が成されましたが効果なく、昨年の兵庫県知事選挙では、数々の偽情報が流された末に、誹謗中傷の標的となった兵庫県議会議員が命を絶つという痛ましい事件がございました。
私自身も昨年は、「論破王」ともてはやされたものとまったく同じ動画に、今年は「論破されて涙目」という真逆のタイトルがついて流布している状態で、要は偽情報・誹謗中傷を流す人にとって中身は無関係、それらしい動画に勝手な煽り文句と誹謗中傷を入れて動画サイトに置けば、面白がる人によって拡散され、少なからぬ人が命を絶つほどに傷つけられ、世論が大きく左右されるということが現在進行形で起こっているわけです。
このような状況で国論を二分する憲法改正の国民投票を行った場合、憲法改正の発議そのものについては、ファクトチェックや法規制等によって一定の適正化が図られたとしても、今度は、その賛否を問う活動をする人、今ここに御列席の各党の議員の方々を始め市民の方々までもが標的にされ、激しい偽情報や誹謗中傷にさらされ、それらによって投票結果が大きくゆがめられる事態が生じる可能性は極めて高いと思います。
我々が公正に形成された民意を適切に反映した憲法改正を行うには、国民投票におけるファクトチェック他の法規制のみならず、まず、今現になされているSNS上での偽情報や誹謗中傷に対し、憲法で保障される言論の自由の観点も考慮しつつ、刑法、情報流通プラットフォーム対処法等の諸法令を改正・整備し、適正な言論空間の確立をする必要があることを強く申し上げます。
今ほどの私の見解に対して、2020年にインターネットの誹謗中傷対策は侮辱罪の厳罰化で事足れりとして現在に至るまで不十分な対策しか打てていない自民党と、外国勢力からの介入に対しては非常に敏感な割に先の兵庫県知事選挙において誹謗中傷の原因となった真偽不明の情報の流布に加担した県議が所属しておられました日本維新の会に御意見を伺わせていただきます。
(憲法審査会での発言から)